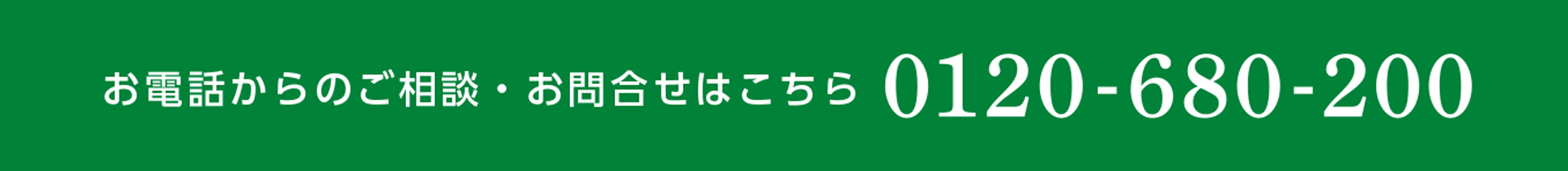一人っ子の相続は大変?知っておくべきデメリットと相続税対策を解説
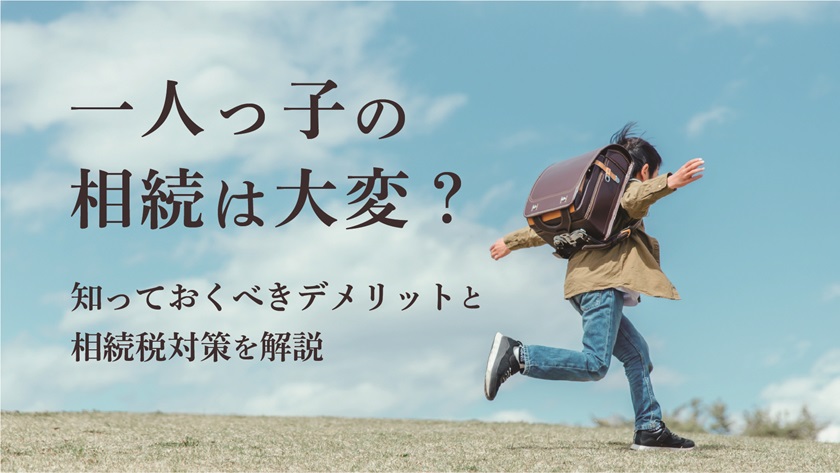
「一人っ子だから相続トラブルは起きにくい」そう思っていませんか?
確かに、一人っ子であれば、他の相続人と意見が衝突するリスクは少ないかもしれません。その一方で、手続きや税金面での負担を一人で背負うリスクがあります。特に、複雑な手続きや税金の問題に不安を抱える方も多いのではないでしょうか。しかし、両親が元気なうちに節税対策や必要な準備を進めておくことで、相続の負担を大幅に軽減することが可能です。事前の準備次第で、将来の相続に対する不安を解消できるでしょう。
本記事では、一人っ子が遺産を相続する際のメリット・デメリットをはじめ、注意すべき3つのポイントを解説します。相続対策として事前に取り組むべき方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
・一人っ子と兄弟姉妹がいる場合との相続の違い
・一人っ子が相続人となる3つのケースと相続割合
・一人っ子が遺産を相続する2つのメリット
・一人っ子が遺産を相続する4つのデメリット
・一人っ子の相続手続きをスムーズに進める流れ
・親ができる一人っ子への相続税対策
・まとめ
一人っ子と兄弟姉妹がいる場合との相続の違い
一人っ子の場合、遺産分割協議が不要なため、相続手続きがスムーズに進むのが大きな特徴です。一方、兄弟姉妹がいる場合は、遺産分割協議が必要となり、相続人間で意見が対立すると手続きが長引く可能性があります。この協議の有無が、一人っ子と兄弟姉妹がいる場合の最大の違いです。また、相続税に関しては、法定相続人の人数に応じて基礎控除額が増減します。一人っ子の場合、法定相続人が少ないため、基礎控除額が低くなりがちです。しかし、基礎控除額を超える財産がなければ相続税は発生しないため、大きな違いが生じるケースは少ないといえるでしょう。
相続税について振り返りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】相続税はいくらから申告する?無税となる金額は?
相続人がいない場合、財産は国の所有となる
相続人がいなければ、故人の財産は最終的に国の所有となります。例えば、一人っ子が両親の財産を全て相続した後、未婚で子もおらず、祖父母や他の親族もいない場合、後に相続人がいなくなる可能性があります。遺言書があれば財産を他の誰かに譲れますが、遺言書がない場合、財産は自動的に国に帰属します。
なお、未婚率の上昇により、相続人がいないケースは増加傾向にあります。国立社会保障・人口問題研究所が推計したデータによると、2050年の未婚率は以下のように予測されています。
✓ 男性:36.5%
✓ 女性:27.1%
「どのように財産を残したいのか」を自ら決めておくことで、後悔やトラブルを防ぎ、大切な財産を未来につなぐことができます。専門家に相談しながら、生前に財産の行き先を明確にしておくことが重要です。
なお、相続税のクロスティでは、相続財産の洗い出しから遺言書の作成まで、トータルでサポートしております。将来の相続に備え、今から準備を進めたい方は、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちら
一人っ子が相続人となる3つのケースと相続割合
一人っ子が相続人になるケースは、大きく分けて以下の3つです。
● 子一人のみが相続人のケース
● 亡くなった方の配偶者と子一人のケース
● 子一人と異母(異父)兄弟がいるケース
一人っ子が相続する場合でも、家族構成や遺言書の有無によって相続割合が大きく変わります。特に異母兄弟がいる場合や不動産が多い場合は、手続きが煩雑になりがちです。スムーズに進めるためには、専門家に相談することをおすすめします。
子一人のみが相続人のケース
他に配偶者や親族がいない場合、相続割合は100%となり、一人っ子がすべての財産を相続します。ただし、法定相続人が一人だと相続税の基礎控除額が少なくなり、税負担が重くなる可能性があります。また、自宅など不動産を相続する場合は、管理や売却の手間が一人に集中する点にも注意が必要です。
亡くなった方の配偶者と子一人のケース
父親または母親が亡くなると、遺産は遺された配偶者と子が受け継ぎます。相続割合は、配偶者が1/2、子が1/2です。例えば、遺産が5,000万円の場合、配偶者と子はそれぞれ2,500万円ずつを受け取ることになります。
子一人と異母(異父)兄弟がいるケース
一人っ子だと思っていても、異母(異父)兄弟が存在するケースがあります。亡くなった方の以前の配偶者や再婚した配偶者との間に生まれた子も、実子として相続権を持ちます。また、結婚していない関係で生まれた子であっても、認知されていれば相続人として一人っ子と同じ相続分を得る権利が認められます。
一人っ子が遺産を相続する2つのメリット
一人っ子が遺産を相続する、主なメリットは以下の2つです。
● 相続トラブルのリスクが少ない
● 手続きがシンプルで進めやすい
それぞれを詳しく見ていきましょう。
相続トラブルのリスクが少ない
一人っ子の場合、相続人は基本的に自分だけ、または配偶者と二人だけになることがほとんどです。そのため、相続財産を巡る意見の対立や感情的な争いが起こる可能性が極めて低くなります。
これに対し、兄弟姉妹がいる場合には、遺産の分け方や財産の評価を巡って意見が対立するケースが少なくありません。一人っ子であれば、こうしたトラブルを回避し、スムーズに相続手続きを進められるでしょう。
手続きがシンプルで進めやすい
一人っ子の相続は複数人で進める場合に比べ、以下のように事務的な負担が軽く済むのが特徴です。
✓ 遺産分割協議が不要
✓ 必要書類が少ない
✓ 手続きが迅速に進む など
複数の相続人がいる場合、財産の分け方について連絡を取り合い、合意に至るまでの時間が必要です。一人っ子であれば、不動産の名義変更や預貯金の引き出しなどもスムーズに進められるでしょう。
一人っ子が遺産を相続する4つのデメリット
一人っ子が遺産を相続するデメリットは、以下の4つです。
● 相続税が高くなる可能性がある
● 相続手続きを一人で進めるため負担が大きい
● 親との遺産分割で争いが起こる可能性がある
● 多額の相続税が課せられる場合がある
デメリットに備えて、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
相続税が高くなる可能性がある
一人っ子の相続では、相続人が少ないため、相続税の基礎控除額が低くなります。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数」です。相続人が1人であれば基礎控除額が少なくなり、相続税を支払うべき金額が増える可能性があります。事前に適切な相続税対策を行うことが、税金の負担を軽減する重要なポイントとなるでしょう。
相続税の負担を抑える方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】相続税の節税対策9選|税理士が相続税対策について徹底解説
相続手続きを一人で進めるため負担が大きい
相続手続きは多岐にわたるため、通常は複数の相続人が協力して進めます。しかし、一人っ子の場合、全ての手続きを自分一人で進めるため、手間や負担が大きくなります。必要に応じて専門家に依頼することを検討するのも一つの方法です。
相続手続きの詳しい流れについては、以下の記事をご確認ください。
【関連記事】税理士に依頼した場合の申告までの流れ~期間目安を解説~
親との遺産分割で争いが起こる可能性がある
配偶者が存命の場合、相続人に加わるため、相続分について意見の食い違いや不仲が原因でトラブルが生じることも考えられます。相続争いを避けるには、日頃から家族で相続に関する話し合いをしておき、事前に認識の共有をしておくことが重要です。
相続トラブルを回避する方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】相続トラブルと特別寄与料|相続人と配偶者が引き起こす事例を紹介
多額の相続税が課せられる場合がある
二次相続では、多額の相続税が課せられる場合があります。具体的には、両親の一方が亡くなると、最初に発生するのが「一次相続」です。その後、もう一方の親が亡くなると「二次相続」が始まります。一次相続では、配偶者(残された親)が「配偶者控除」を受けられるため、相続税の負担は少なくなることが一般的です。しかし、二次相続では配偶者控除が適用されないため、残された一人っ子が多額の相続税を支払うことになります。二次相続では税金が大きくなりやすいため、事前にしっかり準備しておくことが重要です。
二次相続に備えた相続対策について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
【関連記事】二次相続対策をしよう!一次相続との違いや相続税の節税対策
一人っ子の相続手続きをスムーズに進める流れ
相続手続きを円滑に進めるためには、手続きの流れをしっかり理解することが重要です。必要な書類に不備があると、手続きが遅れ、相続税の申告期限に間に合わなくなり、ペナルティを受ける可能性もあります。以下の流れを把握し、効率よく進めるために準備を整えておきましょう。
1. 遺言書の有無を確認する
2. 法定相続人を調査する
3. 相続財産を調査する
4. 遺産分割協議を実施する
5. 相続税の申告・納付を行う
6. 不動産の相続登記や預貯金の相続手続きを実施する
また、稀に亡くなった方の戸籍を調べるうちに、異母兄弟や異父兄弟が見つかり、遺産分けを巡って争いが起こることもあります。これまで一人っ子として過ごしてきた場合、突然の事態に驚き、対応に困惑することがあるかもしれません。亡くなった方の出生まで遡って戸籍謄本を取得し、他に相続人がいないか確認しておくことが重要です。
相続手続きに必要な戸籍謄本の集め方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】相続手続きに戸籍謄本はなぜ必要?集め方や種類、有効期限などを解説
負債が多い場合は、相続放棄も検討する
相続人は、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐことになります。もし負債が多く、負担が大きいと感じる場合は、相続放棄を検討することが有効です。相続放棄を行えば、借金を含むすべての財産を引き継ぐことなく済みます。
また、相続放棄のほかに「限定承認」という方法もあります。限定承認では、プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐため、過度な負担を回避できます。状況に応じて、最適な手続きを選択することが大切です。
相続財産に含まれる権利や義務について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】相続財産に含まれるもの|調べ方や課税される財産との違いとは
親ができる一人っ子への相続税対策
親ができる一人っ子への相続税対策は、以下の5つです。
● 生前贈与を活用する
● 生命保険に加入する
● 孫へ贈与する
● 小規模宅地の特例を適用できるようにする
● 配偶者が健在の場合は、二次相続も視野に入れる
生前に財産を贈与することで、相続時の財産総額を減らせます。その結果、相続税の負担を軽減できるでしょう。ただし、生前贈与には贈与税が課せられることもあります。そのため、贈与税と相続税を比較して、税負担を最小限に抑えるための適切な方法を選択することが重要です。
生前贈与の非課税条件について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】暦年贈与とは|新ルールから使い方、相続税対策における3つの注意点
まとめ
一人っ子の相続では、遺産分割の必要がなく、手続きを自分のペースで進められるため、一見するとメリットが多く感じられるかもしれません。しかし、相続税の負担が大きくなったり、税制上の特典を活用しにくかったりなど、デメリットがあるのも事実です。相続が発生した後でできる対策は限られているため、将来の相続に不安がある場合は、早めに税理士に相談し、適切な対策を講じることをおすすめします。なお、税制は毎年改正されています。相続税に関する最新情報をわかりやすく提供するため、相続税のクロスティでは定期的にセミナーを開催しています。ご自身のケースに合った相続税対策を知りたい方は、お気軽にセミナーへご参加ください。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。
「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)