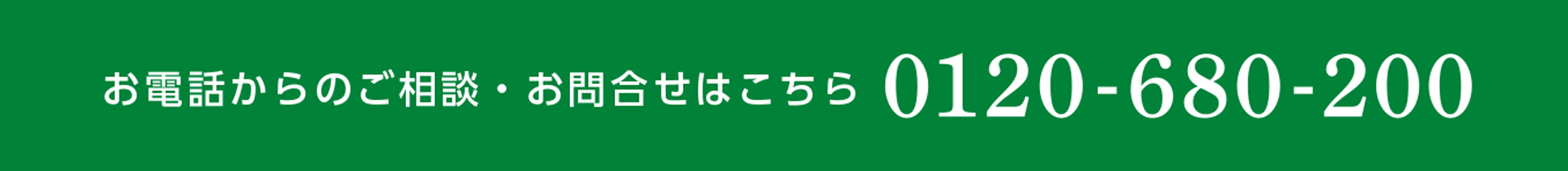暦年贈与とは|新ルールから使い方、相続税対策における3つの注意点

暦年贈与は、生前からできる相続税対策として活用されています。しかし、大切な子どもや孫に、財産をしっかりと残したいと考えていても「いつ、どのように贈るべきか」「どのくらいの金額が適切か」と悩んでいる方も少なくありません。「暦年贈与」と「相続時精算課税」は令和5年度の税制改正で見直されています。法改正前と同じ方法で贈与していると、相続税額は跳ね上がり、相続税対策が無意味になってしまう可能性があるので注意しましょう。そこで今回は、暦年贈与の基本から使い方までわかりやすく解説します。あわせて相続税対策における注意点も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
・暦年贈与と相続時精算課税制度とは
・税制改正で暦年贈与は相続税の対象になる
・暦年贈与を利用する3つの流れ
・相続税対策が水の泡!?暦年贈与3つの注意点
・相続対策には専門家に相談するのも選択肢の一つ
・まとめ
暦年贈与と相続時精算課税制度とは
贈与といえば「暦年贈与」とイメージされることが一般的ですが、それ以外の贈与の仕組みを選択することも可能です。ここでは、暦年贈与と相続時精算課税制度について紹介します。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)において行われる贈与を指します。贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない仕組みを利用して、相続税のかかる財産を減らす相続税対策の一つです。具体的には、毎年の暦年内に贈与を行い、その年の贈与総額が110万円以下であれば、その年に贈与された贈与財産に対して贈与税を支払う必要がありません。令和5年度の税制改正により、暦年贈与に関する生前贈与加算の加算期間が変更されました。
● 令和5年12月31日までの贈与:相続発生3年以内に受けた贈与財産が対象
● 令和6年1月1日以降の贈与:相続発生7年以内に受けた贈与財産が対象
また、贈与者と受贈者の関係によって適用される税率が異なり、特例贈与財産と一般贈与財産といった区分も存在します。上手に活用することで、少しずつ相続財産を減らし、かつ贈与税も回避できるでしょう。
非課税枠110万円
非課税枠の110万円を超える場合は、贈与税が発生します。贈与税は受ける側が負担する税金であり、110万円を差し引いた後の金額が200万円以下の場合は10%、3,000万円を超えると最大で55%の税率が適用されます。贈与額が増えるほど、税率も高くなる仕組みです。また、非課税枠の110万円は贈与を受ける側を基準として計算されます。たとえば、同じ年に父から60万円、母から50万円の合計贈与額が110万円の場合、非課税枠に収まっていると見なされます。一方、父から110万円、母から100万円の贈与を受けた場合はどうでしょうか。両親それぞれの贈与額は110万円の非課税枠に収まっているとしても、子どもは合計で210万円の贈与を受けたと見なされ、110万円を差し引いた金額である100万円に対して贈与税が課税されます。
相続税・贈与税の税率について気になる方は、相続コラム「相続税、贈与税の累進課税制度とは」を参考にしてください。
相続時精算課税
今まで使い勝手が悪かった相続時精算課税制度ですが、今回の法改正により大幅に将来の相続税対策を考えている方に使いやすくなっています。具体的には、令和6年1月1日以降に相続時精算課税制度を選択した場合の贈与でも、年間110万円までであれば贈与税はかかりません。相続時精算課税は、生前贈与の総額2,500万円までを非課税とし、贈与をした方が亡くなった際に、残りの相続財産をまとめて相続税として課税する制度です。生前贈与加算期間に限らず生前に贈与したものはすべて相続税に加算されます。そのため、不動産などを一気に贈与したい方は、暦年贈与制度を選択せずに相続時精算課税を選択する方が多い傾向にあります。その代わり、相続時には加算されるので後払いになります。また、相続時精算課税制度を一度選択すると暦年課税制度に変更できないので注意しましょう。
税制改正について気になる方は、相続コラム「2023年度税制改正によって贈与はどう変わるの?」を参考にしてください。
参考:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
税制改正で暦年贈与は相続税の対象になる
令和5年度の税制改正により、暦年贈与に関する生前贈与加算の加算期間が変更されます。具体的には、令和6年1月1日以降に行われる贈与から、生前贈与加算の加算期間が、相続発生前の贈与受領「3年以内」から「7年以内」に延長されます。生前贈与加算とは、相続が発生した際に、被相続人が亡くなった当日から一定期間内の贈与であれば、相続財産に足し戻して相続税を計算する制度です。贈与税が課せられない額の暦年贈与であっても、生前贈与加算時期によって、相続税の課税対象として計算される可能性があります。
改正前:令和5年12月31日までの贈与の場合
令和5年12月31日までの贈与の場合、相続発生3年以内に受けた贈与が生前贈与加算の対象です。具体的には、贈与税の基礎控除以下でも、相続発生3年以内の贈与は相続税の課税対象となります。一方、3年以内であれば、相続税の課税対象にはなりません。
改正後:令和6年1月1日以降の贈与の場合
令和6年1月1日以降の贈与の場合、相続発生7年以内に受けた贈与が生前贈与加算の対象です。足し戻しの期間が3年から7年に延長しており、これから暦年贈与を検討している方は注意が必要です。
仮に、改正前に贈与していた場合は、令和5年1月から起算して徐々に足し戻し期間が伸びていきます。たとえば、令和2年1月から毎年110万円の贈与を行い、令和5年の2月に亡くなったとします。その場合、7年の贈与加算が開始されていますが、あくまでも7年以内の贈与加算は令和5年1月から起算され、令和5年1月1日以前の贈与に関しては3年を超えていれば足し戻しの対象外です。上記の例に当てはめると、贈与加算対象期間は令和2年2月1日までの3年間となり、330万円が足し戻し対象です。加算期間は、被相続人の死亡当日からカウントされます。そのため、令和2年1月に贈与した110万円は足し戻し対象外です。贈与時期と相続開始時期によって、生前贈与加算の加算期間が変動します。
暦年贈与を利用する3つの流れ
暦年贈与の流れは以下のとおりです。
1. 贈与契約書を作成する
2. 資金の受け渡しをする
3. 110万円以上の場合は贈与税の申告する
それぞれを詳しく見ていきましょう。
1.贈与契約書を作成する
贈与契約書は、贈与の内容を明確に記載する文書です。贈与計画書を作成することで、客観的に贈与の意思を証明できます。契約書には以下の点に留意しましょう。
● 自署と実印の使用
● 住所と日付の記載
● 公証人役場の確定日付を取得
仮に、未成年に対する贈与で「贈与計画書」を作成する場合は、親権者など法定代理人の署名捺印が必要です。
2.資金の受け渡しをする
資金の受け渡しは、通帳に記録が残るように行うことが重要です。たとえば、贈与者の名義の銀行口座から、受贈者の名義の銀行口座へ直接振り込みをするのがいいでしょう。また、贈与契約書の日付と資金の受け渡し日を一致させることも大切です。
3.110万円以上の場合は贈与税の申告する
年間の贈与額が110万円を超える場合、贈与税の申告と納税手続きが必要です。受贈者は贈与税申告書に、贈与をした日付や金額などを記入し、税務署に提出しましょう。納税手続きを通じて、贈与があったことを税務署に証明することで、将来のトラブルを回避できます。
相続税対策が水の泡!?暦年贈与3つの注意点
相続税対策として活用されることが多い暦年贈与。毎年の贈与額が110万円以下であれば、贈与税の基礎控除によって贈与税がかからないと安易に「年間110万円までなら問題ない」と判断してしまうと、贈与税のみならず多額の相続税が課せられる可能性があります。ここでは、暦年贈与する際の3つの注意点を紹介します。
定期贈与に気を付ける
毎年決まった時期に決まった額を贈与していると、税務署に最初から全額を贈与する気だったのではないかと疑われる可能性があります。定期贈与は「500万円を5年にわたって贈与する」といったように、最初から1人にまとまった財産を贈与することを指します。暦年贈与であれば、年間110万円以下は贈与税の課税はありませんが、定期贈与とみなされると多額の贈与税が発生する可能性があります。贈与時期と贈与額などに気をつけましょう。
名義預金の取り扱いに注意する
親が子供にお金を贈与する場合、子供名義の銀行口座に振り込むけれども、実際には親がその口座を管理し、子供がお金を自由に使えないようにするといったケースがあります。このように「贈与したことにする」という考え方は、相続対策する際にありがちな失敗の一つです。名義預金の判断基準は、以下の通りです。
● 預金の資金源
● 贈与契約の成立
● 贈与税の納付
● 資産管理の有無
贈与契約は、贈与者と受贈者の間で成立するものであり、ただお金を振り込んだだけでは実際の贈与とは認められません。その結果、実質的には贈与が行われていないと判断され、相続税対策の効果が失われる可能性もあります。また、名義人が贈与という認識がない場合、贈与税の申告漏れとみなされる可能性があります。預金の名義人が資産を自由に使えるかどうか、資産管理しているかどうかが重要です。名義預金は税務調査が入りやすいので注意しましょう。
相続税の申告漏れについて気になる方は、相続コラム「相続税の申告漏れ!ペナルティとミスがバレる原因とは」を参考にしてください。
誰に暦年贈与するかを検討する
法定相続人以外への贈与は、相続を受けなければ生前贈与加算の対象外です。そのため、暦年贈与では、生前贈与加算の対象とならない孫や子の配偶者などへの贈与が節税効果が高いでしょう。しかし、下記の要件に当てはまる場合は相続発生時に財産を取得するため、生前贈与加算の対象となります。
● 養子縁組
● 死亡保険金の受取人
● 代襲相続人
● 遺言書で遺贈
税理士に依頼しようか悩んでいる方は、相続コラム「相続税申告を税理士に依頼する?メリット・デメリットを徹底解説」を参考にしてください。
相続対策には専門家に相談するのも選択肢の一つ
暦年贈与は相続発生3年または7年以内に贈与した財産は相続財産に含める必要があります。そのため、暦年贈与を相続税対策として行う場合には、相続発生までに時間がないと効果的な手段として意味がありません。また、相続税対策として活用できる非課税制度は暦年贈与以外にも「住宅資金贈与」や「教育資金贈与」などがあります。相続税に強い税理士と協力して、自身の状況に合った最適なプランを立てることが重要です。
相続税のクロスティでは、税理士業界でトップクラスの申告実績を誇り、相続税や生前贈与に関する豊富な知識と経験を持つ税理士が多数在籍しています。一人ひとりの状況に適した節税対策はもちろん、二次相続や将来のトラブルを未然に防ぐ具体的な提案をいたします。
まとめ
暦年贈与を利用することで、贈与税を支払わずに財産を移せるため、相続税対策として活用されます。しかし、暦年贈与するにはいくつかのルールや注意点が存在します。安易な暦年贈与は、逆に多額の贈与税や将来の相続税が課せられる可能性があるので注意しましょう。そのため、暦年贈与と他の非課税制度の併用や相続時精算課税制度の選択など計画的に取り組むことが重要です。相続税や生前贈与に強い税理士に相談することで、個々のケースに適した相続税対策ができるでしょう。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。
「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)