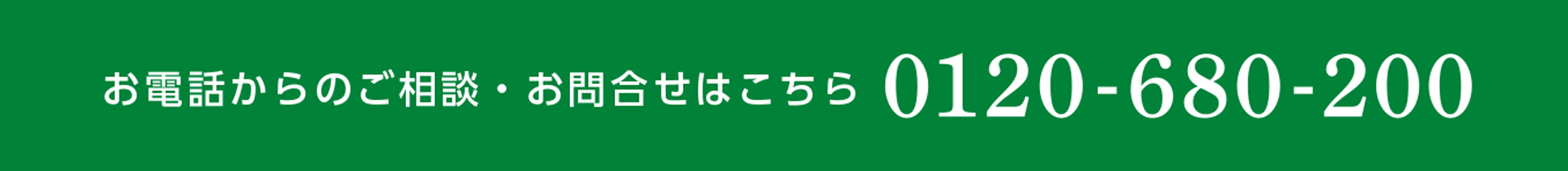相続税の時効とは?5年もしくは7年?成立したら納めなくていいの?
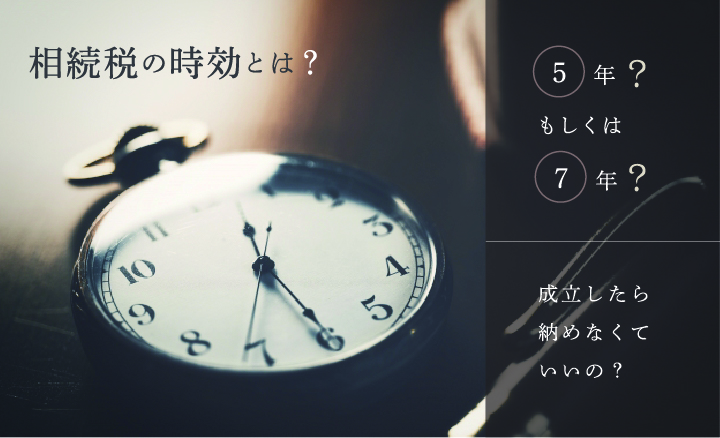
相続をする際、相続税がかかる場合があります。しかし、相続税は時に大きな出費となります。相続税を払ったために手元に財産がほとんど残らなかったというような状況は避けたいでしょう。相続税にも時効がありますが、それでは時効が成立した場合は相続税を納めないでよいのでしょうか?今回は相続税の時効について、そもそもどのようなものなのか、何年で時効になるのか、また、実際に時効を使って相続税の支払いを免れることは可能なのかについて、詳しく解説していきます。
目次
・相続税の時効とは?
・相続税の時効は5年?それとも7年?
・相続税の未納はバレる可能性が高い
・相続税の未納に気づいたらすぐに申告したほうが良い理由
・相続税を納めなかった時のペナルティ
・相続税を納めることが出来ない場合の対処法
・まとめ
相続税の時効とは?

そもそも時効とは、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係に合致するか否かを問わず、権利の取得や消滅という法律効果を認める制度のことをいいます。取得時効と消滅時効があり、相続税の支払い義務については消滅時効の適用を検討します。
相続税の法定申告期限は、相続のあったことを知った日の翌日から10か月以内となります。相続税の納付期限も同じ期限となることに注意が必要です。法定申告期限から一定の期間が経つと、税務署は課税処分を行うことができなくなります。この期間内に申告せず、また税務署から通知なども届かず、相続税の回収がなされない(課税処分が行われない)まま時効の期間を過ぎた場合、相続税を支払う義務を免れることができます。
相続税の時効は5年?それとも7年?

相続税の時効適用の期間については、悪意があるかどうかによって時効の期間は変わります。原則5年として定められていますが、これはわざとではない場合に限り、故意に「偽りその他不正の行為」などにより相続税逃れをしようとして支払わなかった場合は、7年となります。この時効の期間中に、申告・納税をせず、税務署からも課税処分がなされなかった場合、時効が適用できるようになります。
やむを得ず相続税の申告や納税ができなかった場合の時効は5年
わざとではなく、やむを得ない状況で相続税の申告や納税ができなかったという場合もあるでしょう。例えば、相続財産の計算を間違えていて、相続税が発生しないと信じ込んでいた場合です。この場合の時効は原則通り5年となります。
故意に相続税の申告や納税をしなかった場合の時効は7年
故意に相続税の支払いから逃れようと、相続税の申告や納税をしなかった場合の時効は7年です。また、特に悪質だと認められる場合には、重加算税が課せられる可能性があり、その場合は最大、相続財産の40%の税率で納税することになります。またこの重加算税に延滞税も上乗せされるため、当初支払うべきだった納税額よりもはるかに高い額を支払うことになってしまいます。特に悪質であるかどうかの判断は、「故意であったか」よりも「偽りその他の不正があったか」が着眼点となることが多いです。
故意に相続税の申告や納税をしなかった場合
前述の通り、無申告・未納付について、意図的であるかどうかが問題となります。相続人との関係が希薄などで相続した事実を知らなかった場合や、相続額を誤って認識していた場合を除くと、故意に申告や納税をしなかったと疑われることが多いです。特に「偽りその他の不正」があり、悪質性が認められた場合は、最大20%の税率の無申告加算税ではなく、最大40%の税率の重加算税が適用されるなど、追徴課税の税率が高くなる可能性があります。
相続税の申告漏れが最終的に明らかになるのは、税務調査が実施された後です。相続税の調査対象になると、相続人への聞き取り調査に加え、預貯金など財産についての調査も行われます。預貯金は過去10年分をチェックされることもあります。また、相続人に相続税調査の協力を得られないなど、実態の把握が難しいと税務署が判断した場合、取引先や銀行などにも問い合わせる「反面調査」が行われます。
相続税の未納はバレる可能性が高い
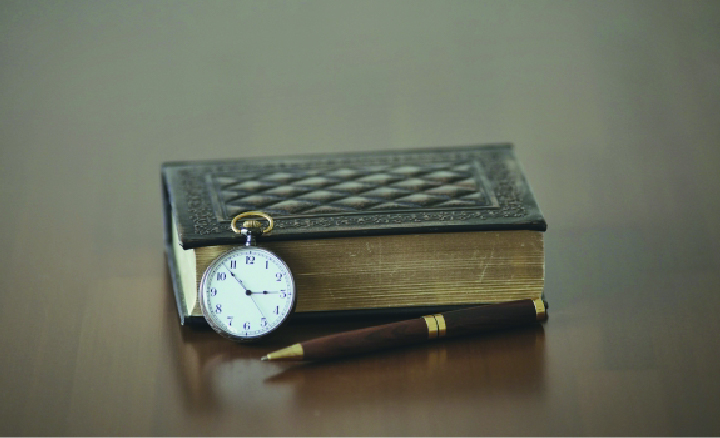
相続税の時効成立は現実的ではなく、実際は税務調査によって指摘され、追徴課税が課されることがほとんどです。相続税の無申告・未納の場合、ほぼ確実に税務調査が行われます。税務署はさまざまな情報を取得することができ、預貯金の動きや不動産の保有状況、株式・国債などの保有状況などを把握しています。そのため、相続税が発生する相続人の相続財産の規模はある程度、既に知っている状態で、申告内容とのずれがないかをチェックし、不審点がある場合に税務調査に入ります。相続税が発生するはずの人物の相続が開始したにも関わらず相続税申告がないとなれば、税務調査は免れられないでしょう。
相続税の未納に気づいたらすぐに申告したほうが良い理由

しかし、相続税の納付義務があるにもかかわらず、相続が発生した後(被相続人が亡くなった後)、相続人にその自覚がなく、税務署から任意の税務調査について連絡あって初めて知ったというパターンもあり得ます。また、相続が発生してからしばらく経ってから遺産が見つかったという場合もあるでしょう。いずれの場合にしても、相続税の未納に気がついた場合は、少しでも早く相続税の申告をすべきです。なぜならば、申告が遅れれば遅れるほど、追徴課税の割合が上がり、支払う納税額が増えてしまうためです。相続税の追徴課税にはどのような種類があるのか、詳しくご紹介します。
相続税を納めなかった時のペナルティ

相続税を納付期限までに申告・納付しなかった場合のペナルティとして、以下の追徴課税が課されます。
● 無申告加算税
● 過少申告加算税
● 延滞税
● 重加算税
過少申告加算税は、実際の相続税よりも少ない額で申告した場合に加算される税です。無申告加算税・過少申告加算税・重加算税の加算税は、申告期限までに正しく申告しなかった税額を基準に、一定の税額を掛けて納付すべき額を算出します。つまり無申告の場合は相続財産全額が課税対象となります。また、延滞税は納税が遅れたことに対するペナルティのため、前述の加算税に上乗せして課され、納付期限から遅れれば遅れるほど金額が上がっていきます。
無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由なく、相続税の申告を期限までにしなかった場合に課される税です。申告が税務調査までにあったかどうかで課される税率が変わります。なお、申告期限から1か月以内に申告した場合は期限後であっても無申告加算税が課税されませんので、まだ相続開始より日が浅い場合は、気づいた時点で専門家に相談して早めに申告されることをお勧めします。
法定申告期限までに申告しなかったが、自主的に期限後申告した場合:
5%
法定申告期限までに申告せず、税務調査が入ってから期限後申告した場合:
追加納付税額のうち50万円までは15%、追加納付税額のうち50万円を超える部分については20%
過少申告加算税
税務調査を受けての過少申告加算税の金額は、追納する相続税の10%ですが、当初の納付額と比較して追納額が多い場合には税率が上がります。
延滞税
延滞税は納付期限を過ぎた場合に課される税です。加算税と併せて課される点に注意が必要です。延滞税は、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課税されます。延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、税率が2種類あります。それぞれの税率で計算した税額を足し算して、実際に支払う税額を算出します。税率は以下の2種類です。
納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間について
年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降について
年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合
重加算税
重加算税は、課税対象の相続財産を悪意を持って隠すなどの隠蔽行為があり、その行為に基づいて過少申告、または期限内に申告しなかった場合に課される税です。重加算税も、申告の有無によって課される税率が変化します。
申告を行なっているが、申告書の内容に隠蔽や偽装がある場合:
35%
申告を行なっておらず、相続財産の隠蔽や偽装がある場合:
40%
重加算税にも延滞税が同時に課されることになりますので、相続財産の50%近くが加算された税額を納付するような場合もあります。また、重加算税が加算される場合、相続税を軽減するための特例を適用することができなくなってしまいます。
相続税を納めることができない場合の対処法

相続税を無申告・未納のまま放置することはデメリットが多く、時効を使って納税義務から免れることも現実的ではありません。相続税が高額になってしまう場合や、相続財産のほとんどが不動産であった場合など、相続税の納付は一括での現金納付が原則のため、支払いが難しい場合もあるでしょう。その場合、相続税を納めるための対処法がありますのでご紹介いたします。
相続税の延納
延納は、分割払いで納付することができる制度です。原則5年以内での支払いとなりますが、相続財産の価額のうち、不動産が半分以上を占めている場合など、一定の条件を満たせば最長20年まで認められています。
物納
物納は、土地や不動産などの相続財産をそのまま相続税の納税に充てることができる制度です。延納も難しい場合に用いられます。物納は、所得税や法人税など、他の国税では認められていないため、相続税特有の制度といえるでしょう。
まとめ

今回は相続税の時効について解説しました。相続税の時効による納税逃れは不可能と言ってもよく、現実的な選択肢ではありません。相続税の無申告・未納に気づいた際は、法定申告期限を過ぎていた場合でも、できるだけ早く申告することが大切です。加算税の計算は条件により複雑になりますので、相続の専門家に早めに相談するようにしましょう。
関連記事
税務調査のリスク軽減!相続税の書面添付制度
相続税の申告について
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。
「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)