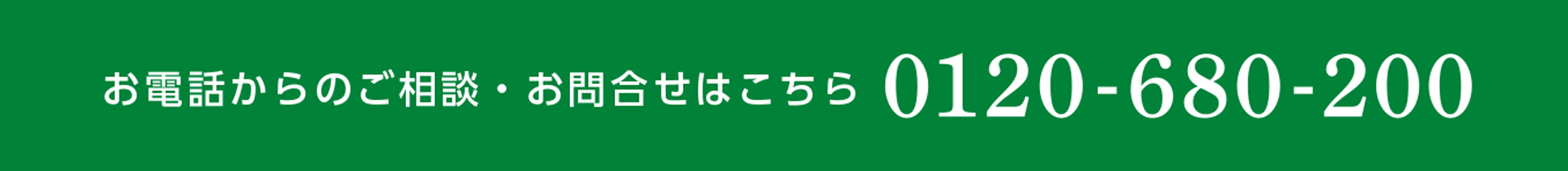土地だけを相続放棄できるのか?手続き方法や必要書類、注意点を解説
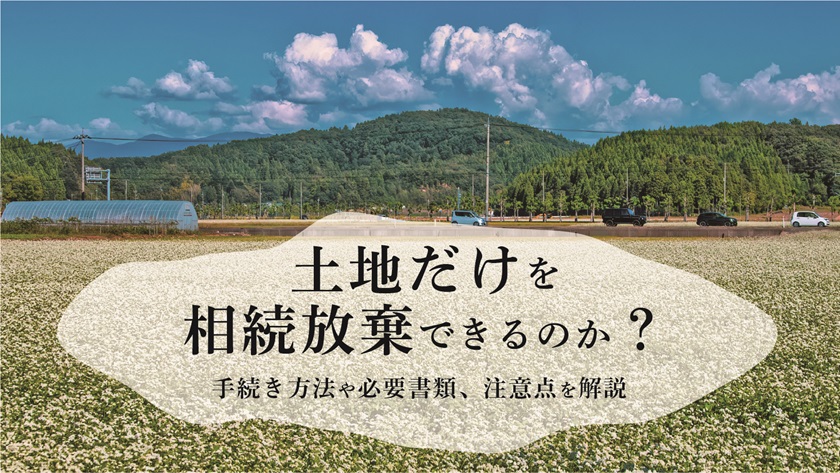
先祖代々引き継いできた土地であっても、引き継がず手放したいと考えるケースは年々増えてきています。特に、立地や条件が悪い土地だと、相続しても使い道がなく、負担になってしまうこともあるからです。そこで検討されるのが相続放棄。しかし、相続財産の一部である土地だけを放棄できるのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続放棄の基礎知識をはじめ、土地のみを相続放棄する方法や必要書類、注意点を解説します。相続土地国庫帰属制度もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
・土地だけを相続放棄することはできない
・そもそも相続放棄とは
・【ケース別】土地相続放棄の手続き
・相続放棄する土地に関する4つの注意点
・まとめ
土地だけを相続放棄することはできない
相続放棄は、すべての財産を放棄する手続きであり、特定の財産のみを放棄することはできません。土地や畑の引き継ぎ手がいない、遠方すぎて管理できないなどの理由から土地を相続できない相続人もいるでしょう。引き継げないと判断した場合、土地の相続放棄を検討されると思います。しかし、相続放棄とは「初めから相続人ではなかった」とみなされる手続きです。土地だけを相続放棄したいと思っても、他の財産も同様に放棄しなければならない点に注意が必要です。また、相続放棄する場合、相続人の代表者だけが相続放棄の手続きをすれば終わりではありません。相続人全員が、各々で相続放棄の手続きをする必要があります。
土地相続で活用できる減額制度を詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】土地評価額の減額制度とは|計算方法や節税ポイントを解説
令和5年法改正|相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を国が所有・管理する制度です。令和5年の法改正により導入され、相続人の管理負担を軽減するとともに、所有者不明土地の増加を防ぐことを目的としています。
最大の特徴は、相続登記後でも手続きが可能であり、期限が設けられていない点です。そのため、土地の売却や活用を試みた後でも、必要に応じて申請を検討できます。一方、相続放棄は全財産を対象とした手続きであり、3ヶ月以内に申請する必要があるため、利用目的や条件が大きく異なります。
制度対象となる土地は、宅地に限らず農地や山林、原野なども含まれるため、固定資産税や維持管理コストの負担が重い土地を手放したい方に適した選択肢といえるでしょう。
しかし、土地を国に引き取ってもらうには法務局への申請が必要です。申請時には土地1筆あたり14,000円の審査手数料がかかり、承認後は10年分の管理費用(一律20万円)を負担金として納付する必要があります。手続きや費用について十分理解した上で、慎重にご検討ください。
そもそも相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方から引き継ぐすべての財産を放棄し、相続人としての地位を辞退することです。通常の相続では、現金や不動産といった資産だけでなく、借金などの負債もまとめて引き継ぎます。そのため、負債が資産を上回る場合には、相続放棄を選ぶことで借金の返済義務を回避できます。ただし、相続放棄を行うには、家庭裁判所への申請が必要です。必要な書類を提出し、裁判所による審査を経て認められた場合にのみ、効力が発生します。家族や親族の間で「相続放棄する」と取り決めただけでは、債権者など第三者に対して効力を主張できない点に注意が必要です。
相続放棄を検討している方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】相続放棄のメリットやデメリットは?
相続放棄の期限
相続放棄は、亡くなった日から3ヶ月以内に、相続人ごとに家庭裁判所に申し立てる必要があります。3ヶ月間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続を受け入れるか放棄するかを判断するための猶予期間です。熟慮期間内に手続きを行わないと、法律上「法定単純承認」とみなされ、以後の相続放棄が原則として認められなくなります。そのため、相続放棄を検討している方は、期間内に行動することが重要です。なお、どうしても3ヶ月以内に結論が出せない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることも可能です。
相続放棄に必要な書類
相続放棄を行うには、以下の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
✓ 相続放棄の申述書
✓ 亡くなった方の除籍謄本一式
✓ 相続放棄する方の戸籍謄本
✓ 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
書類が揃っていないと手続きが進まないだけでなく、相続放棄が認められない可能性もあります。不備があれば家庭裁判所から連絡が入りますが、再提出に時間がかかるケースも少なくなりません。その結果、期限である3ヶ月以内に手続きが間に合わなくなる恐れがあります。必要書類は事前にしっかり確認し、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。
【ケース別】土地相続放棄の手続き
土地相続放棄の手続き方法を、以下のケース別に紹介します。
● 亡くなった人の名義のまま相続放棄する場合
● 相続放棄しないで土地を手放す場合
それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。
なお、相続放棄以外の方法を探している方は、以下の記事もぜひご覧ください。
【関連記事】相続「放棄」ではなく「拒否」する方法とは?
亡くなった人の名義のまま相続放棄する場合
相続放棄をする際、まず知っておくべきことは、土地が未登記の場合、相続手続きを遡って行う必要があるということです。親の土地だと思っていたものが実は先代(祖父など)の名義のままだったというケースでは、相続放棄に入る前に相続手続きから始める必要があります。
未登記土地の相続手続きは、先代の相続人を探すところから始まります。相続人が複数名存在し、その中で既に亡くなっている方がいる場合、配偶者や子たちにも相続権が移るため、相続関係が複雑化してしまいます。そのため、「土地を手放したい」と考えても、相続放棄の手続きに入るまでに時間や手間がかかり、断念せざるを得ない場合があります。
なお、相続登記は2024年4月から義務化されており、土地の所有者が亡くなったことを知ってから3年以内に手続きを行わなければなりません。期限を過ぎると10万円以下の過料が科せられる可能性もあるため、早めに手続きを行うことが大切です。複雑な手続きをスムーズに進めるには、専門家の力を借りることが効果的です。早めに相談することで、トラブルや手間を最小限に抑えられるでしょう。
相続放棄しないで土地を手放す場合
相続放棄せず土地を手放すには、一旦相続登記を行い、土地を引き継いでから、「売却」や「寄付」を検討します。地方の農地や山林であれば、地元の方や自治体に相談することで、スムーズに手放せる可能性があります。例えば、隣接する農家が「耕作地を広げたい」と考えていれば、相談することで土地の売却が成立するかもしれません。また自治体に寄付を検討する際は、地元の役場や土地政策を担当する部署に問い合わせるとスムーズに進みます。事前に寄付が可能か確認してみるといいでしょう。
なお、売却時にかかる税金について詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひチェックしてみてください。
【関連記事】不動産の相続でかかる税金とは|相続時、所有時、売却時の税金を解説
相続放棄する土地に関する4つの注意点
相続放棄する土地に関する注意点は、以下の4つです。
● 次順位の相続人に相続権が発生する
● 管理義務責任が残る
● 相続人全員が相続放棄したら相続財産管理人の選任が必要になる
● 相続放棄できないケースもある
注意点を踏まえた上で、相続放棄を進めるかどうかを検討しましょう。
① 次順位の相続人に相続権が発生する
亡くなった方の子が土地の相続放棄をすると、次順位である祖父母の方々に相続権が移ります。次順位で相続する人に相続放棄した人がその事実をきちんと伝えなければ、知らないうちに土地の相続権を引き継いでいることになります。家庭裁判所からお知らせなどの連絡は来ないため、相続放棄をしたら必ず次順位の人に相続放棄したことを伝えましょう。
なお、1人だけが相続放棄しても次順位に相続権は移りません。複数の子がいる場合、全員が相続放棄をし、家庭裁判所でその放棄が承認されて初めて次順位に相続権が移ります。
② 管理義務責任が残る
固定資産税や土地の維持管理費といった負担からは解放されますが、土地を引き継ぐ人が決まるまでは、管理義務責任が残ります。
管理義務は、相続財産が放置されることで第三者に危害を及ぼすのを防ぐために設けられています。例えば、相続財産に古い家屋が含まれている場合、老朽化により倒壊の危険性があります。そのまま放置しておくと、第三者が事故に遭ったり、無断で住む人が現れて治安が悪化したりする恐れもあります。
万が一、トラブルが発生すると、損害を受けた人が相続放棄をした人に苦情を言ったり、最悪の場合、損害賠償を請求したりすることも考えられます。そのため、相続放棄をしたからといって放置せず、相続財産の管理をしっかりと行うことが重要です。
③ 相続人全員が相続放棄したら相続財産管理人の選任が必要になる
相続人になり得る方が全員相続放棄した場合、相続財産を管理するために「相続財産管理人」を選任する必要があります。相続財産管理人とは、相続人がいない、または相続人全員が相続放棄をした場合に、遺産の管理・処理を行う人です。
相続財産管理人を選ぶには、相続人代表者が亡くなった方の最後の住所地にある家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。もし特定の人を管理人にしたい場合、その人の名前を申立書に記載します。特に決まった人がいなければ、裁判所が適切な人物を選定してくれます。
相続財産管理人が決まると、放棄した相続人の管理責任は終わります。ただし、相続財産管理人には、報酬が発生する点に注意が必要です。報酬は相続財産管理人が土地の処分が完了するまで続きます。管理人が決まるまでに最短2ヶ月ほどかかるため、事前に費用について話し合っておくことが大切です。
④相続放棄できないケースもある
相続放棄を希望しても、以下のようなケースでは原則として認められません。
✓ 相続放棄の期限を過ぎてしまった
✓ 相続財産の一部を使ってしまった
✓ 相続財産の一部を売却(処分)してしまった
相続放棄は、相続財産のすべてに対して行う手続きです。そのため、少しでも相続財産を使ったり売却したりすると、相続したと見なされ、放棄できなくなります。ただし、やむを得ない理由がある場合は放棄が認められるケースもあります。状況に不安がある方は、専門家に相談してみると良いでしょう。
なお、相続税のクロスティでは、相続手続きに関する疑問や不安を解消できるセミナーを定期的に開催しています。今後の手続きに不安を感じている方は、お気軽にご参加ください。
まとめ
相続放棄はすべての財産を放棄する手続きであるため、土地だけの放棄はできません。また、相続放棄をしても、次の相続人が決まるまではその土地に対する管理責任が残ります。相続放棄したからといって土地を放置しないように注意しましょう。相続放棄の期限は3ヶ月以内と非常に短いので、早めに専門家に相談し、検討することをおすすめします。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。
「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)


名古屋総合税理士法人 代表税理士 / 行政書士 / 宅地建物取引士 / 賃貸不動産経営管理士
監修者プロフィール:
相続税に関するセミナー講師を年間100回程度務めるほか、大手信託銀行・不動産管理会社等の税務顧問や、日経新聞社講師、南山大学非常勤講師を務めている。
現在代表を務める名古屋総合税理士法人は、資産家の生前節税対策・法人化節税を得意とし、累計 1,000 件を超える名古屋最大級の相続税申告実績を誇り、相続税相談についての面談数は年間 500 件を超えるほか、数多くの不動産オーナーの顧問税理士を務めている。
【主な活動実績】
・著書「知識ゼロからの相続の教科書」は相続税/贈与税カテゴリーにて、出版週で第1位を獲得
・プロフェッショナルな会計ファームに授与される「Best Professional Firm」を3年連続で受賞
・書籍「相続に強い頼れる士業・専門家50選」に選出
・南山大学の非常勤講師