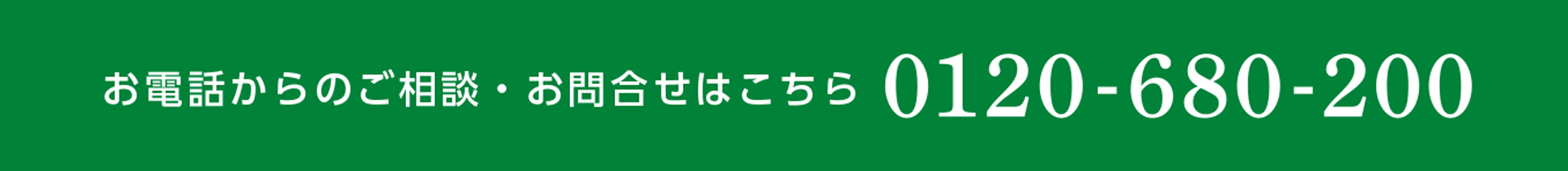死後認知で相続が変わる?相続探偵が迫る隠し子の遺産相続問題

相続が発生した際、最初に行うべきは「相続人調査」です。これによって、予想外の相続人が現れる可能性があります。その中でも、衝撃的なのが「隠し子」の存在です。隠し子の出現は、遺族にとって精神的な衝撃を与えるだけでなく、遺産分割に関わる経済的問題にも影響を与えることがあるのです。
本記事では、隠し子が絡む相続トラブルの実態や、認知請求の方法をわかりやすく解説します。隠し子が発覚した場合の相続手続きについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
・ドラマ「相続探偵」第7・8話から見る隠し子が引き起こす相続トラブルとは
・そもそも死後認知とは
・認知請求の方法
・隠し子に相続させたくない場合の対処法
・まとめ
ドラマ「相続探偵」第7・8話から見る隠し子が引き起こす相続トラブルとは
ドラマ「相続探偵」第7・8話では、探偵・灰絵七生(赤楚衛二)が、かつての恩師である荻久保教授から衝撃的な依頼を受けます。それは、教育学部の名誉教授・薮内教授の死後、週刊誌によって突如報じられた「7人の隠し子」の存在についての調査でした。
妻・佐賀美は、隠し子たちの存在を否定していますが、マスコミはDNA鑑定によって 7人すべてが薮内教授の子であることが証明されたと報道。もしこれが事実なら、5億円の遺産は7人の隠し子にも分配されることになります。
ここでポイントとなるのが、以下の3つのテーマです。
● 隠し子の相続権
● 認知請求の証拠
● 疎遠になっている兄弟姉妹の相続権
それぞれを詳しく見ていきましょう。
隠し子の相続権
隠し子でも、父親に認知されていれば相続権が発生します。認知とは、父親が自分の子であることを正式に認める手続きです。
例えば、生前に父親が「自分の子だ」と認め、戸籍に記載されていれば、法律上の親子関係が成立し、嫡出子と同じ割合で遺産を受け取ることが可能です。しかし、認知されていなければ法的な親子関係がないとみなされ、相続権は発生しません。しかし、生前に認知がなかった場合でも、家庭裁判所で「死後認知」を請求することで、相続権を得られる可能性があります。
なお、隠し子が特別養子縁組によって新たな親のもとへ養子に出されている場合、相続権はなくなります。特別養子縁組とは、実の親との法的な親子関係を完全に解消し、新しい養親と親子関係を結ぶ制度です。例えば、両親の離婚後に子が特別養子縁組をした場合、実父との親子関係は法律上なくなります。そのため、相続で隠し子として名乗り出ても、すでに親子関係が断たれているため、遺産を受け取る権利はありません。
認知請求の証拠
認知請求する際は、親子関係を証明するための証拠が必要です。ドラマ「相続探偵」でも、週刊誌が行ったDNA鑑定により、薮内と7人の隠し子が親子関係にあることが明らかになったという報道がありました。これにより、隠し子を名乗る7人が登場し、全員が薮内の子である可能性が示されたのです。
しかし、灰江はその結果に疑問を抱き、再度DNA鑑定を求めます。ところが、隠し子たちは全員鑑定を拒否し、調査は難航します。それでも灰江たちは、隠し子たちの髪の毛やタバコの吸い殻などを持ち帰り、なんとかDNAを採取し鑑定を行いました。その結果、7人全員が薮内の子ではないことが判明します。
ただし、現実の裁判では、本人の許可なくDNA鑑定を行うことは権利侵害として不法行為になる可能性が高いため、勝手に採取するのはおすすめできません。なぜならDNAは個人情報保護法で守られており、警察が行う場合でも令状が必要だからです。認知請求する際は、法的に認められる方法で証拠を集め、慎重に手続きを進めることが重要です。
なお、認知請求において証拠となるのは、必ずしもDNA鑑定だけではありません。裁判では、父親との関係を示すさまざまな資料が有力な証拠となります。例えば、父親がDNA鑑定を拒否した場合、裁判所は「拒否するのは自分が父親であることを隠したいからではないか」と推測し、親子関係を認める判断に傾く可能性があります。また、妊娠・出産の経緯をまとめた陳述書や、父親とのメールやSNSでのやり取りも、親子関係の証拠として提出できます。
疎遠になっている兄弟姉妹の相続権
兄弟姉妹であっても、必ずしも相続権があるとは限りません。法律上、兄弟姉妹が相続人となるのは、故人に配偶者や子、親・祖父母といった直系尊属がいない場合に限られます。
ドラマ「相続探偵」では、資産家の薮内に一卵性双生児の兄・郷田蜆(ごうだ しじみ)がいることが判明します。郷田は「藁の上からの養子」として、貧しい家庭に引き取られ、虐待を受けて育ちました。「藁の上からの養子」とは、本来は生まれてすぐ養子に出されたのに、戸籍上では最初から養親の実子として届け出る方法です。かつては役所の管理が甘く、実際に行われていた脱法的な手法ですが、もちろん違法であり、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に問われる可能性があります。
一方で、薮内は裕福な家庭で成功。郷田は境遇の違いに絶望し、薮内の死後、偽のDNA鑑定を使って遺産を奪おうと企てます。今回のケースでは、郷田が法的に薮内の兄弟と認められるかどうかがポイントです。養子縁組などの正式な手続きがなされず、戸籍上も他人の子として育てられていた場合、法律上の兄弟関係は認められず、相続人にはなれません。そのため、長年疎遠になっていた兄弟姉妹が相続を主張する場合は、戸籍謄本などの公的記録を確認し、法的な立場を明確にする必要があります。
そもそも死後認知とは
死後認知とは、父親が亡くなった後に、婚姻関係のない相手との間に生まれた子(非嫡出子)が、法的に親子関係を認めてもらう制度です。父親の死後でも、親子関係が認められれば非嫡出子でも正式な相続人として、法定相続分を受け取れるようになります。
しかし、すでに遺産分割協議が終了している場合、後から認知されると、最初から遺産分割をやり直さなければならなくなり、他の相続人の取り分に大きな影響を与える可能性があります。そのため、金銭的な解決策を講じることで他の相続人との調整を図るものとされています。
遺産分割協議について振り返りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
【関連記事】遺産分割協議書を作成できる人とは?自分で作成する5つの手順を解説
死後認知の時効は3年
死後認知の請求は、父親が亡くなってから3年以内に行わなければなりません。時効を過ぎると、原則として認知の請求は認められなくなります。例えば、父親が3年前に他界していたことを最近知ったというケースでも、死亡日から3年が経過していれば、訴えを提起できなくなります。一方で、やむを得ない事情がある場合には、時効の起算点が「死亡の事実を知ったとき」となった判例もあります。
なお、父親が生きている間であれば、子が生まれてから何十年経過していても、認知の訴えを起こせます。
認知請求の方法
認知請求の方法は、大きく分けて以下の2つです。
● 任意認知
● 強制認知
認知が成立すると、法律上の子として、扶養請求権や相続権などの権利を得ます。ただし、相続権を得ることにはプラスの財産だけでなく、負債も含まれるため、相手男性が借金を抱えていた場合などは注意が必要です。
任意認知とは
任意認知とは、父親が自らの意思で子との法的な親子関係を認めることを指します。任意認知の方法は、以下の3つです。
✓ 胎児認知
✓ 出生後認知
✓ 遺言認知
胎児認知は、子が生まれる前に行う方法です。民法第783条に、「父は、胎内にある子でも認知できる」とされています。父親が子が生まれるまで存命できない可能性がある場合などに備え、母親の承諾を得たうえで市区町村役場に認知届を提出します。
一方、出生後の認知は、子が生まれた後に行う方法です。母親の承諾は不要ですが、子が成人している場合は本人の同意が必要です。
遺言認知は、父親が遺言書に認知の意思を記載することで成立します。遺言の効力は父親の死後に発生し、法律上の子として認められます。ただし、遺言の執行には遺言執行者の指定が必要です。遺言執行者がいない場合、相続人などが家庭裁判所に申し立て、選任手続きを行わなければなりません。
強制認知とは
強制認知とは、相手男性が自発的に子との親子関係を認めない場合に、家庭裁判所を通じて認知を強制的に決定してもらう手続きです。これにより、相手男性の意思に関わらず、子との法的な親子関係が確定します。
強制認知を求める場合、まず認知調停を申し立て、その後調停が不成立の場合には認知訴訟を提起します。認知訴訟では、通常、DNA鑑定を含む親子関係の証明が必要です。また、調停や裁判は通常、1~2ヶ月に1回のペースで行われ、複数回にわたって進行するのが一般的です。そのため、「子を認知してもよい」という裁判所の認定を得るまでには、時間がかかることを覚悟しておく必要があります。
隠し子に相続させたくない場合の対処法
隠し子に遺産を相続させたくない場合、法的に認められた権利とはいえ、突然現れた相続人と遺産を分けることに抵抗を感じる遺族は少なくありません。特に、故人と長年生活を共にしてきた家族が、隠し子の存在を受け入れがたいと考えるのも無理はないでしょう。こうした状況を避けるための方法として、以下の3つが考えられます。
● 相続放棄を促す
● 遺言書を作成する
● 専門家に相談する
それぞれを詳しく見ていきましょう。
相続放棄を促す
本人の意思による相続放棄が成立すれば、法律上は最初から相続人でなかったものとみなされるため、遺産を受け取る権利はなくなります。
「相続探偵」の中でも、本物の隠し子が現れた際、死後認知の訴えを起こして親子関係を証明するか、協議の上で解決金を受け取るかという選択肢が提示されました。現実の相続でも、隠し子と話し合い、相続を放棄する代わりに一定の金額を支払うことで争いを回避する方法が取られることがあります。
ただし、相続放棄は本人の自由な意思で行うものであり、強制はできません。無理に放棄させようとすると、隠し子の正当な権利を侵害することになり、法的なトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
遺言書を作成する
遺言書があれば、以下の方法を指定できるため、相続トラブルを防ぐことが可能です。
✓ 子の認知
✓ 相続の割合
✓ 遺産の分割方法 など
ただし、法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されています。たとえ遺言書で「隠し子には相続させない」と書いたとしても、認知されている場合は、遺留分を請求される可能性があります。そのため、遺言書を作成する際には、遺留分を考慮した内容にすることが重要です。
専門家に相談する
隠し子が関わる相続は複雑になりやすく、適切に対処しなければ法的トラブルに発展する可能性があります。円満に解決するためには、早めに専門家のアドバイスを受け、適切な準備を進めることが大切です。相続専門の税理士や弁護士などに相談することで、遺産分割協議や相続税の申告、認知請求への対応などもスムーズに進められるでしょう。
なお、相続税のクロスティは、遺言の作成から相続税申告までトータルでサポートしております。遺産相続をめぐるトラブルを未然に防ぎたい方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
相続トラブルを防ぐためには、事前の準備が欠かせません。「相続探偵」に描かれているように、相続発生後に隠し子の存在が明らかになると、遺族は予期せぬ事実に直面し、感情的・経済的な大きな負担を背負うことになります。相続は、単に財産を分けるだけの問題ではなく、故人の意思と家族の想いを尊重し、全員が納得できる形で解決することが理想です。円満な解決のためにも、早めに専門家のアドバイスを受け、適切な準備を進めることをおすすめします。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。
「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)