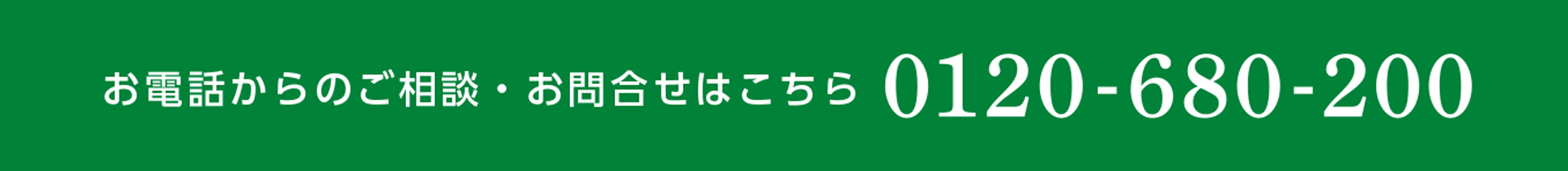後継者がいない会社の相続対策|相続探偵が警告する生前相続の重要性
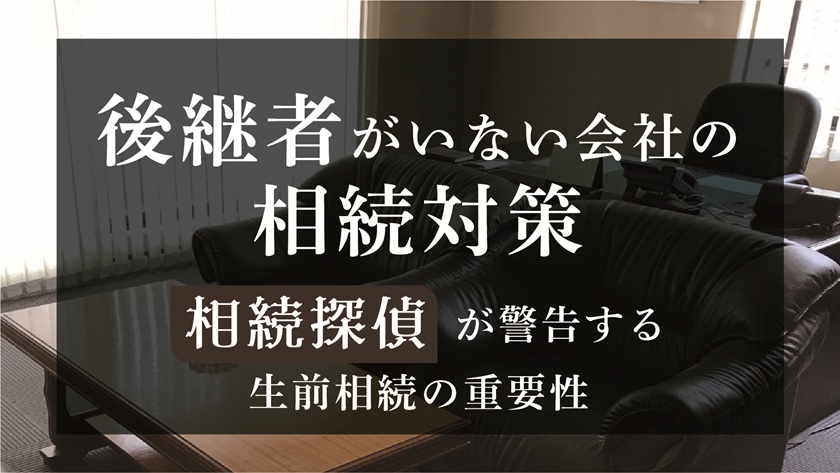
会社を経営するうえで、「事業を誰に託すか」は避けて通れない問題です。実際に多くの企業が「後継者不在」という深刻な状況に直面しています。後継者が決まらないまま相続を迎えると、事業承継をめぐって親族間でもめたり、相続税の支払いに苦慮したりして、会社の存続自体が危ぶまれることもあります。だからこそ、元気なうちに「誰に継がせるか」を明確にし、早めに備えておくことが重要です。
本記事では、後継者不在の企業が直面する相続問題と、生前に行うべき対策の重要性について詳しく解説します。事業を未来へ残す承継方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
・ドラマ「相続探偵」第6・7話が警告する生前相続の重要性
・先祖が遺した事業を守るために生前にできる相続対策
・跡継ぎが見つからなければ、他の承継方法を検討しよう
・まとめ
ドラマ「相続探偵」第6・7話が警告する生前相続の重要性
ドラマ「相続探偵」第6話では、事業承継の難しさと生前の相続対策の重要性が描かれています。舞台となるのは、地域に長年愛されてきた銭湯「笑福湯」。
相続探偵・灰絵七生(赤楚衛二氏)行きつけの銭湯ですが、時代の変化と社会情勢の影響を受け、経営が厳しくなっていました。娘夫婦は事業を引き継ぐ意向がなく、先祖が残した事業をどう続けるかが大きな問題となっています。店主が廃業を視野に入れている中で、孫娘がその事業を引き継ぎたいという意思を示します。
ここでは、ドラマが警告する生前相続対策の重要性を、以下の5つのテーマを通じて詳しく掘り下げていきます。
● 生前相続とは
● 相続税の落とし穴
● 跡継ぎがいない会社
● 孫への事業承継
● 不動産売却による詐欺事案
それぞれを詳しく見ていきましょう。
生前相続とは
ドラマの中で使われる「生前相続」という言葉は、法律上の正式な用語ではなく、実際には「生前贈与」に該当します。
相続とは、誰かが亡くなったときに財産が相続人へ引き継がれるものです。この際、遺産額に応じて相続税が課せられます。つまり、相続する財産が多ければ多いほど、相続税の負担も大きくなる仕組みです。
一方、生前贈与は、財産を生きている間に他の人に渡す行為です。生前贈与をうまく活用することで、相続発生時の遺産を事前に分散できるため、将来の相続税負担を軽減できます。ただし、贈与する金額や相手によって贈与税がかかるケースもあります。効果的に活用するには、制度についてよく理解し、計画的に行うことが大切です。
相続税と贈与税の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】相続税と贈与税どっちが得?税率、特例の活用や相続税を減らす3つのポイントを解説
相続税の落とし穴
ドラマ「相続探偵」の中で、銭湯の店主が「自分が亡くなったら土地を売れば相続税も払えるし、娘たちにも迷惑をかけない」と語る場面があります。一見、親としての思いやりに満ちた判断ですが、相続税は相続発生を知った日から10ヶ月以内に申告・現金一括納付が原則です。実際、役所への届け出や葬儀、法要などの手続きに追われ、あっという間に申告期限が迫ってしまうケースも少なくありません。
また、相続財産に不動産が多い場合、現金化できる資産が少なく、納税資金の確保が難しくなります。土地を売却して相続税を支払うつもりでも、申告期限前に売却が成立する保証はありません。急いで土地を売ろうとすると、買い叩かれてしまうリスクもあります。事業や家族を守るためには、元気なうちから相続対策を進めることが大切です。
相続税の概要について振り返りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
【関連記事】相続税はいくらからかかる?妻・親子別の無税ラインと申告基準を解説
跡継ぎがいない会社
かつては、経営者の子が家業を継ぐのが当たり前でした。しかし、価値観は大きく変化し、親の会社を継がない選択をする子も増えています。同時に、親自身も「子には好きなことをしてほしい」と考え、事業承継を強く望まないケースも多く見受けられます。特に、業界が衰退している場合、経営者が「このまま自分の代で廃業しよう」と考えるケースも少なくありません。
例えば、ドラマで描かれた銭湯のように、現在の温浴業界は厳しい状況にあります。公衆浴場の数は年々減少し、燃料費の高騰によるエネルギーコストの負担増加などで、事業継続が困難になっている施設が多いのが現状です。このような状況で事業を続けたいと考えるのであれば、次世代への引き継ぎ方法を早急に考えなければなりません。
跡継ぎがいない場合の承継方法は多岐にわたりますが、どれを選ぶにしても、できるだけ早い段階で準備を進めることが事業の未来を守るためには欠かせません。生前にしっかりと準備しておくことで、円滑な事業継続への道が開けるでしょう。
孫への事業承継
孫への事業承継には、相続税の2割加算や贈与税の負担が重くのしかかります。
例えば、生前に株式を贈与すればスムーズな承継が可能ですが、高額な贈与税が発生します。一方で、孫を養子にすれば相続税の基礎控除額は増やせるものの、2割加算の壁は避けられません。そのため、複数の対策を組み合わせ、税負担を最小限に抑えることが重要です。
なお、事業承継は、単に「誰が継ぐか」ではなく、「どう未来へ橋を架けるか」の問題です。家業が引き継がれなければ、その歴史も信頼も、時代の波に消えてしまいます。しかし、「守りたい」意志を持つ孫が現れたなら、その思いを現実のものとする環境を整えることこそが、現経営者に課せられた最後にして最大の使命と言えるでしょう。
相続税の2割加算とは何か知りたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
【関連記事】孫は相続税の2割加算の対象?適用ケースと相続税負担を軽減する方法
不動産売却による詐欺事案
相続において不動産売却は、一度決断すると後戻りはできない重大な選択です。にもかかわらず、不動産業界は市場規模が大きいため、正規の取引の裏で、悪質な業者による詐欺や不正も後を絶ちません。中でも、「早く売らないと損をする」といった不安を煽り、不当に安い価格で売却させる手口は典型的な詐欺パターンの一つです。
ドラマ「相続探偵」では、銭湯「笑福湯」の店主が、土地の汚染を口実に騙されそうになるシーンが描かれました。実際には汚染の事実はなく、詐欺師がヒ素を持ち込んで、土地の価値を下げて安く買い取ろうと画策していたのです。さらに、調査を進めると、汚染を証明するはずの不動産業者が詐欺の前科を持つ偽業者であることが明らかになりました。
詐欺に巻き込まれないためにも、適正な価値を見極め、信頼できる専門家と相談しながら進めることが大切です。
なお、相続税のクロスティでは、税理士や司法書士をはじめとした専門家が連携し、複雑な相続問題にワンストップでサポートします。相続について不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。
先祖が遺した事業を守るために生前にできる相続対策
事業の存続には、「経営の引き継ぎ」と「財産の承継」の両方を考えた対策が必要です。計画的に準備しておくことで、経営のバトンをスムーズに渡し、後継者や家族の負担を軽くできます。事業を守るためにも、以下のような対策を検討しましょう。
● 後継者を早めに決め、経営を引き継ぐ準備する
● 遺言書を作成し、誰に何を譲るかを明確にする
● 事業用資産を生前贈与し、相続税の負担を軽減する
● 生命保険を活用して、相続税や事業資金を確保する
● 不動産の評価減を活用し、税負担を抑える
● 家族信託を利用して、資産管理をスムーズにする
● 事業承継税制を活用し、自社株の引き継ぎを円滑にする
● 養子縁組して、相続税の基礎控除を増やす
● 夫婦間贈与を利用して、配偶者の生活を安定させる など
相続対策は、生前に行動することで実現できるケースがほとんどです。その中でも特に重要なのが「遺言書の作成」です。遺言書があれば、誰が何を相続するのか、どのように事業を承継するのかが明確になり、家族間のトラブルを未然に防げます。しかし、遺言書がなければ、法律に従って遺産が分割されるため、当初の意図とは異なる結果を招く可能性があります。後継者や資産分割について明確にしておくことで、家族や従業員が安心して業務に専念でき、事業の円滑な継続が可能になるでしょう。
なぜ「今」相続対策すべきなのか
相続対策は、早く始めるほど「事業も財産もスムーズに引き継ぐ」ことが可能になります。事業承継には、後継者の育成や資産の引き継ぎなど、長期的な視点と計画的な準備が欠かせません。経営を安心して託すためには、一朝一夕ではなく、時間をかけて段階的に進めていく必要があります。
また、財産の承継に関しては、生前贈与を活用することで、相続税の負担を大きく減らせます。例えば、子2人に毎年110万円ずつ贈与した場合、10年で2,200万円、20年で4,400万円もの資産を非課税で移転できる計算になります。年間110万円までの贈与は非課税で行えるため、早いうちからコツコツ贈与を始めるほど、多くの財産を税負担なく移すことが可能です。加えて、生前贈与は単なる節税対策ではなく、家族と資産について話し合うきっかけにもなります。お金の話はタブー視されがちですが、事前に「何を・誰に・どう渡すか」を明らかにすることで、相続発生後のトラブルを避けることにもつながります。
「いつかやろう」ではなく、「できる今から」動くことが、先祖から引き継いだ事業を次世代につなぐ最大の備えとなるでしょう。
後継者を決めたら、相続人の遺留分を配慮することが大切
後継者を決めたら、相続人全員の遺留分も考慮することが大切です。遺留分とは、相続人が受け取るべき最低限の財産の割合を法律で保障した制度です。
例えば、事業を後継者に承継させる際、土地や施設などの主要な財産を後継者に集中させるケースがよくあります。しかし、たとえ遺言書に「財産は後継者に譲る」と記載しても、他の相続人が自分の取り分が少ないと感じ、不公平だと感じることがあります。また、遺留分を無視すると、相続人間で激しい争いを引き起こす原因ともなりかねません。そのため、後継者に事業を託すためには、相続人全員の権利を尊重し、事前にしっかりと対策を講じることが重要です。
跡継ぎが見つからなければ、他の承継方法を検討しよう
後継者が決まらないからといって、事業の存続を諦める必要はありません。状況に応じて、以下の方法を検討することが大切です。
● 社内承継
● 第三者承継(M&A)
● 株式公開(IPO)
など
社内承継は、長年会社を支えてきた役員や従業員に事業を譲る方法です。社内の人材なら会社の理念や業務を熟知しているため、比較的スムーズな承継が可能です。また、親族や社内に適任者がいない場合、M&Aを活用して外部の企業や個人に売却する方法もあります。相乗効果を期待できる企業に売却すれば、会社の成長にもつながる可能性があるでしょう。他にも、株式を公開(IPO)すると、投資家からの資金調達が可能になり、事業拡大のための資金を確保できます。どの方法を選ぶにせよ、後継者や買い手が安心して経営を引き継げるよう、財務状況を整理し、適切な税務対策を実施することが重要です。
なお、相続税のクロスティは、グループ全体で円滑な事業承継を支援し、会社の未来を築くためのサポートを行っています。事業承継の準備を進めたい方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
事業承継は、単なる経営権の引き継ぎではなく、家族関係・税務・法律が絡み合う複雑なプロセスです。しかし、多くの中小企業では準備不足が原因で相続トラブルが発生し、事業継続が危ぶまれるケースも少なくありません。
特に、遺言や承継計画がないまま経営者が急逝すれば、経営に関与していなかった親族が会社の意思決定に関わる可能性もあり、経営の方向性が揺らぐリスクが高まります。また、後継者の育成や資産の整理には、通常5〜10年程度の準備期間が必要です。だからこそ、「まだ大丈夫」と先延ばしにせず、早めに行動を起こすことが重要です。
先祖から受け継いだ大切な事業を、次世代へと確実に引き継ぐためにも、税理士などの専門家に早めに相談し、計画的に進めることをおすすめします。
最後に
相続税の申告手続きは、相続税のクロスティにお任せください
私たち、相続税のクロスティは、税理士法人の相続税を専門とする事業部から発足し、母体である名古屋総合税理士法人は創業以来50年以上、愛知県名古屋市にて東海エリアを中心に相続税専門の税理士として、皆さまの相続手続きをお手伝いしてまいりました。
相続税は税理士にとっても特殊な分野の税目です。相続税の高度な知識だけでなく、民法や都市計画法など幅広い知識が必要な他、年月をかけ培った経験やノウハウが大変重要になる分野です。税額を安くする制度は多数ありますが、その選び方ひとつで大きくお客様の納税負担は変わります。
故人から受け継いだ大切な遺産を、少しでもお守りすべく、私たち相続税のクロスティは各士業(司法書士、弁護士、不動産鑑定士、行政書士など)や国税OBなど各専門家と提携し、お客様におすすめの制度と対策をご提案させていただいております。私たち相続税のクロスティは「相続でお困りの方を一人でも減らしたい」という想いから、初回のご相談は無料で対応いたしております。「相続の仕組みを知りたい」「相続税申告が必要かわからない」「まずは見積りだけほしい」など、まずはどんなことでもお気軽にご相談ください。ぜひ、お会いできる日を楽しみにしております。
初回の無料相談は「ご来社による相談」「オンラインツールを使った相談」が可能です。名古屋に限らず日本全国の相続のご相談に対応いたします。
ご来社いただく場合、本社(名古屋市中区栄)または池下駅前本部(名古屋市千種区池下)のいずれかにてご対応させていただきます。
電話でのお問い合わせは24時間受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。
「個別説明会」開催のご案内 相続のことは実績と経験が豊富な相続税専門の税理士にご相談を。
運営:名古屋総合税理士法人
(所属税理士会:名古屋税理士会 法人番号2634)